「なんとなく税金を払いすぎている気がする…」
「控除とか非課税制度って結局どう使えばいいの?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。実は、控除や非課税制度を活用するだけで、同じ年収でも年間10万円以上の差が生まれるケースもあります。
この記事では、初心者でも理解しやすいように、主要な制度の仕組みと活用方法を独立系FPがやさしく解説します。
- 自分の年収を守る方法がわかる
- 年末調整や確定申告で損をしない方法がわかる
- 知らないと損をする所得控除がわかる
年末調整や確定申告が迫ったいま、節税するだけでは意味がありません。節税の方法を活用しながら年収を守り、お金を増やすことが大切です。今年だけでなく、来年以降も活用できるよう、今からお金のリテラシーを高めていきましょう。
家計の見直し方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。

なぜ「控除や非課税制度」を知らないと損をするのか

控除や非課税制度は、国が家計をサポートするために設けている仕組みです。しかし、学校で詳しく教えてもらえるわけではなく、常に制度は変化しています。
そのため、知っているかどうかで結果が大きく変わります。年収が同じでも、制度を活用している人は年間数万円から数十万円の差が出ることも少なくありません。
とくに、医療費控除やふるさと納税、iDeCo、NISA、住宅ローン控除は家計改善に直結する代表例です。
年収が同じでも手取りが変わる仕組み
税金は「課税所得」に対して課されます。つまり、所得控除を使って課税所得を減らせば支払う税金が減り、手取りが増える仕組みです。
たとえば年収500万円の会社員でも、所得控除を上手に活用すれば、年間20万円前後の手取り増加も夢ではありません。日々、節約を心掛けるよりも、効果が出やすいのが所得控除の特徴です。
年末調整や確定申告をしなければ、所得控除の活用はできません。なお、所得の申告をしない場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

控除や非課税の制度を知らないと損する理由
控除や非課税制度の特徴は、「知っている人だけが得をし、知らない人は損をし続ける仕組み」になっている点です。
とくに、家計に直結する制度は数多く存在するにもかかわらず、その多くが申請制となっています。控除や非課税制度は、「国が勝手にやってくれるもの」ではなく、知識をもって自分から活用して初めて効果が得られる仕組みです。
せっかくお金を稼いでも、制度を知らず活用できなければ税金を多く納めることになり、手元に残るお金は少なくなってしまいます。
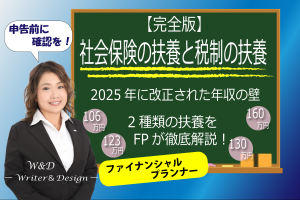
FP(ファイナンシャルプランナー)は、制度を活用しながら家計に役立つ最新の情報を持っています。長期的に役立つ家計戦略と家計改善なら、『W&D-Writer&Design-』の無料FP相談を活用してみてください。
W&D-Writer&Design-のFP相談では、オンラインによる相談が可能です。ご自宅から足を運ぶことなく、お金の悩みを相談できます。独立系FPであるため商品の営業販売はなく、あくまで悩みや不安を解決することを目的としています。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
\まずはLINEで気軽に相談/
知っているだけで得をする主要な控除・非課税制度

ここからは、初心者でも使いやすく、節税効果の高いものに絞って解説します。
医療費、住宅、投資、教育など幅広いシーンで使える制度を取り上げているため、自分の家庭状況に照らし合わせながら読み進めると理解が深まります。「今年の家計」と「未来のお金」を両方守るために、活用できる制度から今日のうちに押さえておきましょう。
医療費控除|金額が不足するならセルフメディケーションも
医療費控除は、1年間の医療費が一定額を超えた場合に税金が戻ってくる仕組みです。
「治療目的の支出」は幅広い費用が対象となり、通院の交通費、ドラッグストアの薬、子どもの医療費も含めて合算できます。夫婦や家族で医療費を合算して所得控除にできることも、大きな特徴です。
さらに、病院にあまり行かない人には「セルフメディケーション税制」という選択肢もあり、市販薬の購入でも控除が受けられる場合があります。領収書やレシートを保管するだけで準備ができるため、家計との相性が良い制度です。
ふるさと納税|実質2,000円負担で返礼品
ふるさと納税は、寄附をすることで住民税・所得税が控除され、返礼品まで受け取れる人気の制度です。そのため、知っている人は多いことでしょう。
年収に応じた上限額内で寄附をすれば、実質負担は2,000円で済み、家計のプラスにつながります。ふるさと納税は家計改善につなげやすく、食費や日用品を返礼品に選べば「節約効果」も生まれます。
会社員ならワンストップ特例制度を使えば確定申告も不要で、初心者でも始めやすい制度です。
iDeCo|老後資金づくり&全額所得控除
iDeCoは老後資金を積み立てながら、掛金がそのまま所得控除になる強力な節税制度です。
たとえば毎月2万円を積み立てた場合、年間24万円の所得控除となり、年収や税率によっては年間数万円の節税効果が期待できます。運用益も非課税となるため効率的な資産形成が可能です。
ただし原則60歳まで引き出せないため、「老後資金」という目的を持って長期で活用するのが向いています。
NISAの運用益が非課税|長期投資と相性◎
NISAは2024年から制度が拡充され、投資で得た利益が非課税になる長期運用向けの制度です。
複利効果を最大限活かせるうえ、売却による非課税枠の再利用も可能です。なお、NISAで得た利益は、非課税であることから所得として申告する必要はありません。
NISAは教育資金・老後資金・将来の資産形成に幅広く使えます。「投資=リスクが不安」という人でも、積立投資を選べば値動きの不安を抑えながら着実に増やす選択が取れるため、初心者にこそメリットの大きい制度です。
住宅ローン控除|最大級の節税効果
住宅ローン控除は、新築・中古に関わらず住宅取得者にとってもっとも節税効果の大きい制度のひとつです。年末の住宅ローン残高に応じて住宅ローン控除を利用できます。
控除期間は13年など長期にわたるため、総額で見ると数百万円単位の効果があるケースも考えられます。ただし、購入時期や床面積などの条件が細かいため、確認不足による“控除もらい損ね”が起きやすい制度の代表例と言っても過言ありません。マイホームを購入する前に必ず知っておきたい制度です。

ひとり親控除・寡婦控除|申請すれば家計支援に直結
ひとり親世帯や配偶者と死別・離婚した人が対象です。死別した場合は寡婦控除となり、夫と死別した女性で条件を満たした人しか利用できません。一方、ひとり親控除はシングルマザーだけでなく、シングルファーザーも対象です。
ひとり親控除や寡婦控除は、子育て世帯を支援する制度として重要です。対象となれば税負担が大きく軽くなるだけでなく、自治体によっては別の支援制度とも併用できる場合があります。
しかし、存在を知らず申請していないケースも多く、「知識格差」が最も出やすい分野です。該当する可能性がある場合は必ず確認しておきましょう。
教育資金の非課税制度|相続税の対策に役立つ
教育資金一括贈与の非課税制度は、祖父母などが子や孫に教育資金を一括贈与する場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる仕組みです。
進学準備や学費の支援に有効で、教育費負担の軽減に役立ちます。将来の教育資金は家計負担が大きくなりやすいため、「早めの準備」がのちの家計を助けることにつながります。進学を控える家庭にとっては知っておきたい制度です。
ただし、贈与されたお金を学費以外に使用した場合は、非課税の対象が最大500万円となります。
この非課税制度は、2026(令和8)年3月末までに入金された贈与までが対象です。しかし、これまで何度も延長されてきた制度であるため、今後も延長される可能性はあるでしょう。
参照:国税庁|祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
控除を最大化するために今日からできること

控除や非課税制度を効果的に活用するためには、「知識を持って制度を選ぶ」ことが大切です。併せて、3つのポイントを理解して実行することも欠かせません。
- 支出の記録
- 証明書類の保管
- 年末調整と確定申告の違いを理解する
所得控除のなかには、年末調整で完結しない制度が多く、確定申告をしないことで控除が未適用のまま終わってしまうケースが非常に多く見られます。制度ごとの“申告タイミング”を把握することが節税効果を最大化するうえで重要です。
制度を知ることは第一歩に過ぎません。「使い続けて家計の仕組みに組み込む」ことで手取り改善の効果が毎年積み上がります。これから年末調整や確定申告の時期を迎えるにあたり、ぜひ3つのポイントを確認しておいてください。
年間の支出を記録し「控除対象」を意識する
控除制度は、年間の支出を正確に把握しておくほど有利になります。とくに、控除の対象となりやすい場面が多いのは以下の3つが挙げられます。
- 医療費
- 教育費
- 寄付金
上記の費用は、年間を通じてレシートや領収書を整理しておくだけで「申請のし忘れ」を防げます。家計簿アプリなどを活用すれば支出の分類や年間管理も簡略化でき、確定申告時の作業もスムーズです。
「どの支出が控除対象になるのか」を意識するだけで、年間数万円単位の節税につながることもあるため、家計管理と控除制度はセットで考えるのが理想です。
2025年最新版のおすすめ家計アプリは、以下の記事で紹介しています。併せてご覧いただき、ぜひ活用する際の参考にしてください。

証明書類を保管して申告時の漏れを防ぐ
節税を成功させるためには、領収書・レシート・支払証明書などの保管が欠かせません。医療費控除や寄附金控除などは、支出が確認できなければ控除が受けられず、本来戻るはずのお金を逃してしまうケースが多く見られます。
とくに、医療費の領収書は1枚1枚の金額が小さくても、年間で合算すると控除の対象金額に達することも珍しくありません。ファイルで月別に管理したり、スマホアプリで撮影してデータ保管しておくと、確定申告の際にスムーズです。
証明書類を習慣的に保存しておくだけで、節税の成功率は大きく上がります。「後でまとめる」ではなく「その都度保存」が、控除の取りこぼしを防ぐ最もシンプルな方法です。
年末調整と確定申告の違いを理解する
節税を最大化するには、「年末調整」と「確定申告」の違いを正しく理解しておくことが重要です。
会社員の多くは「年末調整だけで完結する」と考えがちです。しかし、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)・雑損控除・副業の経費計上などは確定申告をしなければ控除の対象となりません。
年末調整は会社が給与所得に関する税金を自動計算してくれる仕組みですが、対応範囲は生命保険料控除や扶養控除など一部に限られています。そのため「会社が全部やってくれる」と思い込んでしまうと、控除の機会損失が生まれます。
年末調整と確定申告の違いを理解しておくことで、「何を自分で申告すべきか」が明確になり、控除の取りこぼしを防げます。控除制度をより多く活用する家庭ほど確定申告の必要性が高まるため、申告の対象と仕組みを理解しておくことが節税への近道です。
控除や非課税制度をFPに相談するメリット

控除や非課税制度は組み合わせることで効果が大きく変わります。
しかし「制度の存在を知ること」と「自分の家庭に合う制度を選ぶこと」はまったく別の問題です。とくに、子育て世帯・住宅購入予定・老後資金準備・保険加入・投資初心者などケースごとに最適解は異なります。
たとえば、兵庫県尼崎市のように人口構造がファミリー層中心の地域では、教育費と住宅費が家計の大部分を占める傾向があり、控除制度を家計戦略と合わせて活用することで長期的な手取り改善が可能になります。
制度そのものを知るだけでなく、「制度を家計に最適化すること」がFP相談の大きな価値だと言えるでしょう。
家計改善とライフプランまで一気に見直せる
制度は単体で見ると「得か・損か」で判断しがちですが、ライフプランに合わせて活用すれば効果は最大化します。
教育費ピーク、住宅ローン返済、老後資金準備など、それぞれのタイミングで活用すべき控除の優先順位は変わります。FP相談では制度の知識だけでなく、「家計のゴールに合わせて制度をどう使うか」まで踏み込めることが大きな特徴です。
FP相談を活用することで、最短で家計改善につながる効果が得られます。

制度を組み合わせると節税効果は何倍にもなる
控除や非課税制度は、単体でも効果のある制度は多くあります。しかし、以下のように制度を掛け合わせることで、節税効果と将来効果を同時に狙うことができます。
- 住宅ローン控除 × NISAで運用
- iDeCo × 社会保険料控除
- ふるさと納税 × 医療費控除
家計に合う制度を適切な順番で選べば、「手取り」「将来資産」「可処分所得」のすべてを改善できるポイントが大きな魅力です。
このように、家計に合った制度の順序設計がFPの得意分野です。「我が家に合った制度の組み合わせは?」と疑問を感じたら、ぜひFPに相談してみてください。
W&D-Writer&Design-のFP相談では、オンラインによる相談が可能です。ご自宅から足を運ぶことなく、お金の悩みを相談できます。独立系FPであるため商品の営業販売はなく、あくまで悩みや不安を解決することを目的としています。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
\まずはLINEで気軽に相談/
よくある質問【Q&A】

ここからは、制度や非課税制度を詳しく知らない場合、つまづきやすいポイントをQ&A形式で紹介します。
制度を上手に活用するためにも、ぜひ参考にしてみてください。
Q1. 控除と非課税は何が違うのですか?
控除は「税金の計算対象となる所得を減らす仕組み」で、結果として所得税や住民税が軽減されます。一方、非課税は「そもそも税金がかからない仕組み」です。
たとえば 、iDeCoは掛金が所得控除の対象となる一方、NISAは運用益が非課税になります。両方を正しく使うことで節税効果を最大化できます。「控除で手取りアップ」「非課税で資産形成効率アップ」という役割の違いを知っておくことが重要です。
Q2. ふるさと納税と医療費控除は併用できますか?
「ふるさと納税」と「医療費控除」は併用可能です。
ただし、2つはそれぞれ別の仕組みであることを理解することが大切です。役割の違いから、計算方法や控除反映のタイミングが異なります。
- ふるさと納税(寄附金控除):住民税の軽減
- 医療費控除:課税所得を減らす控除
どちらも確定申告をすることで控除を適用できますが、会社員の場合は医療費控除は確定申告が必須、ふるさと納税はワンストップ特例を使えば確定申告不要です。
なお、ふるさと納税を活用する際は、住民税の控除上限を超えないよう注意しておく必要があります。
Q3. 年末調整だけで節税は十分ですか?

すべての会社員が年末調整だけで節税できるとは限りません。
年末調整は「会社ができる範囲の調整」に限られます。医療費控除・寄附金控除・副業の経費・雑損控除・住宅ローン控除(初年度)などは年末調整では対応されず、確定申告が必要です。
年末調整だけで完結している人は控除の取りこぼしが発生している可能性が高く、「確定申告をする人のほうが年間の手取りが増えやすい」というのが現実です。

Q4. NISAとiDeCoはどちらを優先すべきですか?
目的と家計状況によって異なります。
- 流動性(いつでも売却可能)を重視:NISA
- 節税効果と老後資金の確実な積み立てを重視:iDeCo
両方の活用が理想ですが、初心者はまずNISAから始め、家計に余裕があればiDeCoを追加する形が現実的です。
流動性を重視するならNISA、老後資金と節税重視ならiDeCoがおすすめです。
Q5. 住宅ローン控除は誰でも使えますか?
住宅ローン控除の利用には条件があります。利用するためには、床面積・ローン年数・所得上限・新築か中古かなどの基準を満たさなければなりません。
また、控除を利用する年の年末時点のローン残高に連動するため、繰上返済のタイミングによって控除額が減るケースもあります。とくに、住宅ローン控除を初めて利用する際は、年末調整でも申告しなければなりません。
「知らずに損をする」ことが多い制度なので、購入前に制度設計とライフプランを確認することが大切です。
Q6. 扶養控除と配偶者控除の違いは?
扶養控除と配偶者控除には、以下のような違いがあります。
- 扶養控除:扶養する親や子に対して適用される控除
- 配偶者控除:専業主婦(主夫)など配偶者に対して適用される控除
いずれも所得要件があり、年収103万円・106万円・130万円など所得のボーダーラインを意識することで手取り額を増やせる可能性があります。
なお、扶養控除と配偶者控除は対象が異なるため併用できません。扶養している子どもが19歳以上23歳未満なら、「特定親族特別控除」を利用して、所得制限の緩和や控除額の増額が可能です。
配偶者が働いている場合でも、所得金額によっては「特別配偶者控除」を利用できる場合があり、所得控除を諦めずにすみます。知っていれば得する控除なので、ぜひ意識して活用してください。
Q7. 専業主婦でも節税できますか?

所得のない専業主婦でも可能です。節税方法は、以下のようなケースが挙げられます。
- 医療費控除:家族で合算して世帯の節税
- ふるさと納税:世帯の節税
- 生命保険料控除:配偶者が契約者なら保険料控除を利用して節税
- NISA:運用益が非課税となる節税効果
また、「配偶者控除」と「特別配偶者控除」の仕組みを理解していれば、働き方の調整で手取りが増える場合もあります。

Q8. 自営業と会社員では控除は変わりますか?
共通制度もありますが、利用できる所得控除の範囲が異なります。
会社員は年末調整後、利用できない控除がある場合は確定申告(修正申告)で残りの所得控除を利用できます。一方、自営業は必ず確定申告しなければならず、以下のような所得控除を活用できます。
- 事業経費の計上
- 青色申告控除
- 小規模企業共済の活用
自営業者のほうが控除の自由度が高い反面、所得控除の知識がなければ損が生じやすい実情があります。
Q9. 医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できる?
医療費控除とセルフメディケーションは、併用できません。
医療費が年間10万円、または所得の5%を超える場合は、医療費控除のほうが有利となるケースが多くあります。一方、病院にほとんど行かない家庭なら、セルフメディケーション税制が有効です。
医療費控除やセルフメディケーションを利用する際は、領収書の保管が判断の第一歩となります。
Q10. 節税はいつから始めるのがベスト?
早いほど有利となるため、気づいた今から始めることをおすすめします。
とくに、NISAやiDeCo、住宅ローン控除などは「時間の経過=節税」や「非課税の恩恵を積み上げる制度です。1年遅れるだけで将来の可処分所得に大きな差が生まれます。「制度を知った日がスタート日」と考えるのが正解です。
【まとめ】制度を知る人が得をする時代

控除や非課税制度は、知らなければ一生払い続ける税金を減らし、将来の資産形成にも直結する重要な仕組みです。
医療費控除・ふるさと納税・NISA・iDeCo・住宅ローン控除は、家計改善の柱となる制度であり「知る → 使う → 続ける」の流れを習慣化できるかどうかで大きな差が生まれます。
節税効果は年単位で積み上がるため、早く知った人ほど有利になり、対策が遅れるほど損をし続ける構図です。まずはできる制度から一つでも行動し、家計の手取り改善につなげていきましょう。
控除制度を最大化するには「制度の知識」と「家計戦略」の両方が欠かせません。
もし自分の家庭に合う制度の選び方や優先順位に迷う場合は、一度ご相談ください。
W&D-Writer&Design-のFP相談では、オンラインによる相談が可能です。ご自宅から足を運ぶことなく、お金の悩みを相談できます。独立系FPであるため商品の営業販売はなく、あくまで悩みや不安を解決することを目的としています。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
\まずはLINEで気軽に相談/





