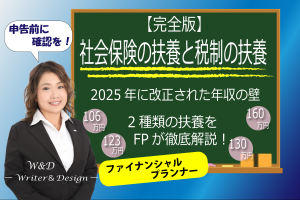「教育費って大学まででどれくらいかかるの?」
「3,000万円の教育資金が準備できなかったら子どもはどうなる?」
子どもが大学まで行くと教育費が3,000万円と聞いて、驚く人や疑いを持つ人は少なくありません。実際、3,000万円の教育費は一定の条件で進学した場合の最大値です。
では、どのような進路なら教育資金が高くなるのか気になる人も多いことでしょう。とはいえ、希望に満ち溢れた子どもの将来、必要な学費はできるだけ準備してあげたいものです。
この記事では、教育費が3,000万円という噂は本当なのか、FP視点で詳しく解説していきます。また、最新情報をもとに、教育費のシミュレーションやライフステージ別に、学費がかさむポイントも紹介します。
- 教育費が最大3,000万円の真偽や実態がわかる
- 進路ごとに必要な教育費や学費がわかる
- ライフステージ別での教育費のかかり方と利用できる制度がわかる
ぜひこの記事を参考に、計画的な教育資金の準備方法について考えてみてください。また、教育資金に不安がある場合は、利用できる制度も紹介しているので、ぜひ検討してください。
教育費3,000万円の根拠と実態

大学までに教育費が3,000万円かかるというのは本当です。
ただし、すべての子どもに一律で必要になるわけではありません。教育費3,000万円という金額は「幼稚園から大学まで私立に通った場合」の総額を示しています。進学ルートによって必要となる教育資金は大きく変動し、公立中心なら約1,000万円前後で収まるケースもあります。
最新情報から見える「教育費3,000万円」の根拠
文部科学省「子供の学習費調査令和5年度」によると、教育費は次のように推移しています。
| 1年間の教育費 | 令和5年度 | 令和3年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学校区分 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 |
| 幼稚園 | 18万4,646円 | 34万7,338円 | 16万1,526円 | 30万8,909円 |
| 小学校 | 33万6,265円 | 182万8,112円 | 35万2,566円 | 166万6,949円 |
| 中学校 | 54万2,475円 | 156万359円 | 53万8,799円 | 143万6,353円 |
| 高校(全日制) | 59万7,752円 | 103万283円 | 51万2,971円 | 105万4,444円 |
また、日本政策金融公庫「令和3年度 教育費負担の実態調査結果」によると、大学4年間で必要となった教育費は以下のような調査結果があります。
| 4年間の教育費 | 令和3年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|
| 国公立 | 743万円 | 783万2,000円 |
| 私立(文系) | 951万6,000円 | 949万7,000円 |
| 私立(理系) | 1,083万4,000円 | 1,109万2,000円 |
幼稚園から大学まですべて私立で進学した場合、教育費の総額は以下のとおりです。
- 私立大学(文系):2,806万812円
- 私立大学(理系):2,937万8,812円
上記は約2,800万円~3,000万円となり、これが「教育費3,000万円」の根拠となっています。
公立・私立別の教育費シミュレーション
幼稚園から大学までの教育費は進学状況によって異なります。公立と私立でどのように教育が変化するのかは、以下を参考にしてください。
| 学校区分 | 公立の場合 | 私立の場合 |
|---|---|---|
| 幼稚園3年間 | 約56万円 | 約105万円 |
| 小学校6年間 | 約202万円 | 約1,100万円 |
| 中学校3年間 | 約163万円 | 約468万円 |
| 高校3年間 | 約180万円 | 約318万円 |
| 大学4年間 | 約743万円 | 約950~1,100万円 |
| 合計 | 約1,344万円 | 約2,941~3,091万円 |
すべて公立を選んで進学すれば約1,350万円の教育資金が必要です。しかし、私学を含みつつ進学すると、2,000万円を超える可能性が高くなると考えられます。
【公立・私立別】大学までの教育費シミュレーション

公立と私立で教育費がここまで差が出てしまう理由は、公立は授業料が安く抑えられている一方、私立は授業料や施設費が高額になるからです。とくに、私立小学校や私立理系大学は費用が突出して高くなる傾向があります。
どのような進学をするかは、子どもの希望も大きな選択要素ですが、家庭の経済状況によって、選べる進学先が変わるケースも少なくありません。
子どもの学費がどれくらい必要か悩んだときは、公立と私立の教育費シミュレーションを参考にしてください。
ケース① オール公立の教育費
すべて公立で進学した場合、教育費の総額は約1,300万円前後です。児童手当や毎月の積立、公的な制度を利用しつつ、進学費用をカバーできる家庭も多いと考えられます。
ケース② 高校から私立の場合の教育費
高校からは私立に進学する場合、教育費の総額は約1,700万〜1,850万円と考えられます。小学校や中学校から塾へ通い始めたり、受験費用の負担があったりなど、想定以上に出費が増える傾向があります。
ケース③ 大学のみ私立の教育費
公立高校から私立大学へ進学する場合、教育費の総額は約1,700万円前後になると予想されます。とくに、理系学部を選択すると進学費用は高くなります。
ケース④ オール私立の場合の教育費
すべて私立で進学した場合、教育費の総額は約2,900万〜3,100万円です。教育費がピークを迎えるときに家計への負担が非常に大きく、早い段階での資金計画が必須です。
【ライフステージ別】大学までにかかる教育費の特徴

教育費は、子どもの年齢によって特徴が異なります。ライフステージ別で教育費の特徴を紹介するので、ぜひ参考にしてみてださい。
未就学児|0~6歳
幼稚園や保育所は、2019(令和元)年10月より無償化制度が始まりました。対象となっているのは以下の施設です。
| 幼児教育・保育の無償化制度 | 利用料が無償化となる対象 | 概要 |
|---|---|---|
| 幼稚園 保育所 認定こども園 地域型保育 企業主導型保育事業 など | 0歳~2歳 ※住民税非課税世帯が対象 | 送迎・食材料・行事費用は自己負担 ※第2子は半額、第3子以降は無償 |
| 3歳~5歳(※1) | ||
| 3歳~5歳(※1) ※年収360万円未満相当の世帯 ※第3子以降の子ども | 副食(おかず・おやつ)費用は免除 | |
| 幼稚園 | 3歳~5歳(※1) | 月額の上限2万5,700円を超えると 自己負担 |
| 幼稚園の預かり保育 | 利用日数に応じた無償化 | 月額の上限1万1,300円を超えると 自己負担 |
| 認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 | 0歳~2歳 ※住民税非課税世帯が対象 | 月額の上限4万2,000円を超えると 自己負担 |
| 3歳~5歳(※1) | 月額の上限3万7,000円を超えると 自己負担 | |
| 発達支援 | 3歳~5歳(※1) | 利用料以外は自己負担 |
(※1)満3歳になった後の4月1日~小学校入学前までの3年間
未就学児は無償化になったとはいえ、通園費や給食費、園外保育などの行事費用は必要です。また、0~6歳は、スイミングや体操などの習い事で教育費がかさみやすくなっています。
小学生|7~12歳
公立小学校では、授業料や教科書代が無償で、すべての生徒が対象です。一方、私立小学校は無償化の対象外で、授業料を負担しなければなりません。
なお、公立・私立ともに授業料以外の費用は自己負担です。教育資金に不安がある場合、一定の条件を満たせば、公立・私立ともに「就学援助制度」を利用できます。就学支援制度では、学用品や給食費、修学旅行費を支援してもらえます。
- 生活保護を受けている
- 自治体の定める所得を下回っている
※自治体ごとに所得額は異なる
公立小学校なら授業料の無償化に伴い、学費の負担は抑えやすくなります。しかし、塾やスポーツクラブなどの授業料がかかり、公立小学校でも教育費が高くなる傾向があります。
私立小学校へ進学する場合、施設の整備や多岐に渡る授業で、幼稚園生活の充実度が高くなる一方、教育費の負担は増加傾向です。そのため、出産時から計画的な教育費の準備を始める必要があります。
中学校|13~15歳

中学生も、小学生と同様、公立と私立によって無償化の対象が異なります。
公立なら授業料は無償ですが、私立は授業料の負担しなければなりません。所得の条件が該当する世帯は、就学援助制度を利用できるため、自治体に確認してみてください。
中学生はクラブ活動や受験対策で塾へ通うケースが多いため、学校外の教育費が増加する時期です。私立の場合、とくに施設利用料や就学旅行の積立費用が高く、教育費が増加しやすくなります。
なお、地域によっては今後、学校のクラブ活動を地域クラブに移行されていきます。働き方改革による教師の負担軽減や少子化を背景に、民間と地域、行政の協働でクラブ活動が継続されることになるでしょう。そのため、所属するクラブ活動によっては教育費が高くなる可能性があります。
当事務所のある尼崎市では、2028(令和9)年度末を目途に、中学校内すべてのクラブ活動が終了し、地域クラブへ移行されます。

直営地域クラブ・認定地域クラブ、指導者登録制によって、利用するクラブで利用料が異なるため、小学校の間に確認しておくことが大切です。
高校|16~18歳
2010年から開始された「高等学校就学支援金制度」は、2020年4月から私立高校へと拡充され、「私立高校授業料実質無償化」が誕生しました。
「高等学校就学支援金制度」とは、返還不要の授業料支援です。条件に該当すれば、公立・私立ともに授業料は無償となります。
| 高校の無償化 | 対象となる学校 | 条件 |
|---|---|---|
| 高等学校等就学支援金 | すべての高等学校(公立・私立) 中等教育学校(後期課程) 高等専門学校(1~3年) 特別支援学校 専修学校高等課程 海上技術学校 など | 年収約910万円未満の世帯が対象 |
| 私立高校授業料実質無償化 | 私立高等学校 | 年収約590万円未満の世帯の支援額が上がる ※1所得額によって上限が異なる |
新たに加わった「私立高校授業料実質無償化」は、私立高校が対象です。「高等学校等就学支援金」の所得要件で支援額が減額されていた世帯も、支援額が引き上げられます。
なお、「私立高校授業料実質無償化」の上限額は、以下の計算式で支給される上限額が決まります。
上記で算出された金額から、上限額を求めます。
- 15万4,500円未満:最大39万6,000円を支給
- 15万4,500円~30万4,200円:11万8,800円を支給
高校の無償化は、世帯の所得によって上限額が異なります。そのため、高収入で扶養が少ない世帯の場合、必ずしも無償化に該当するとは限りません。
大学|19~22歳
大学への通学方法によって、教育費は異なります。一人暮らしなど自宅外から通う場合、学費に加えて子どもの生活費がかかります。
日本政策金融公庫「令和3年度 教育費負担の実態調査結果」によると、自宅外から大学へ通う子供への仕送り額は、年間95万8,000円が平均値です。自宅外通学を始めるために、1人あたり38万7,000円の負担が発生しています。
なお、大学の学費も2020年4月より無償化が始まっています。ただし、世帯年収が380万円以下で、資産条件を満たしている場合のみです。
- 生計維持者が1人:資産が1,250万円未満
- 生計維持者が2人:資産合計が2,000万円未満
支援額を一覧で紹介するので、ぜひ参考にしてください。
| 高等教育の修学支援新制度 | 国公立 | 私立 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上限額の目安 | 入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | |
| 昼間制 | 大学 | 28万円 | 54万円 | 26万円 | 70万円 |
| 短期大学 | 17万円 | 39万円 | 25万円 | 62万円 | |
| 高等専門学校 | 8万円 | 23万円 | 13万円 | 70万円 | |
| 専門学校 | 7万円 | 17万円 | 16万円 | 59万円 | |
| 夜間制 | 大学 | 14万円 | 27万円 | 14万円 | 36万円 |
| 短期大学 | 8万円 | 20万円 | 17万円 | 36万円 | |
| 専門学校 | 4万円 | 8万円 | 14万円 | 39万円 | |
| 通信課程 | 大学 短期大学 専門学校 | - | - | 3万円 | 13万円 |
※上記は住民税非課税世帯の場合における上限額
※住民税非課税世帯に準ずる世帯の場合、目安年収として300万円未満なら上記表の2/3、380万円未満なら1/3が支援の上限額となる
また、返済不要の奨学金制度「日本学生支援機構(JASSO)」も利用でき、学生生活を送るために通学状況ごとに毎月支援額を受け取れます。
| 給付型奨学金 | 国公立 | 私立 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 通学方法と上限額 | 自宅 | 自宅外 | 自宅 | 自宅外 | |
| 昼間制・夜間制 (月額) | 大学 短期大学 専門学校 | 29,200円 (33,300円) | 66,700円 | 38,300円 (42,500円) | 75,800円 |
| 高等専門学校 | 17,500円 (25,800円) | 34,200円 | 26,700円 (35,000円) | 43,300円 | |
| 通信課程 (年額) | 大学 短期大学 専門学校 | - | - | 51,000円 | |
※上記は住民税非課税世帯の場合における上限額
※住民税非課税世帯に準ずる世帯の場合、目安年収として300万円未満なら上記表の2/3、380万円未満なら1/3が支援の上限額となる
※()内は生活保護世帯の上限額
また、2025年度からは、多子世帯向けの制度が始まっています。多子世帯の意味や支援条件について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

大学までの教育費をどう準備する?FPが提案する方法

教育資金は「気づいたら不足していた」というケースが少なくありません。だからこそ、早めの準備が重要です。
そこで、独立系FPの視点で、教育費の準備方法を3つご提案します。
児童手当を積み立てる
0歳から高校卒業するまでに受け取れる児童手当の総額は、第1子のみの場合234万円です。これを使わず積み立てれば、大きな教育資金の柱になります。
現状の児童手当は、子どもの年齢や人数によって以下のように定められています。
| 児童手当の金額 | 3歳未満 | 3歳~高校生 |
|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 月額1万5,000円 | 月額1万円 |
| 第3子以降 | 月額3万円 | |
2024(令和6)年10月からは、児童手当における所得制限が撤廃されています。
また、2026(令和8)年度からは、子ども・子育て支援金制度の拡充が予定されています。従来の児童手当に加え、子ども1人当たり平均約146万円の増額となる見込みです。そのため、1人あたり約380万円もの教育資金を準備できることとなります。
学資保険・NISAを活用する
計画的に教育資金を積み立てる方法として、学資保険やNISAの活用があります。
- 学資保険:確実に積み立てたい人向け
- NISA:長期運用で効率よく積み立てたい人向け
生命保険会社が販売する学資保険は、毎月保険料を支払って、あらかじめ決めた時期にまとまった金額を受け取れる特徴があります。保険料は加入時の保護者(契約者)や子どもの年齢、満期までの加入期間によって異なります。
誕生と同時に学資保険に加入する場合、保護者の年齢が若いほど保険料が安くなるため、加入するなら1歳でも早く加入することがおすすめです。
NISAは長期の積み立てや分散投資に適した資産形成方法です。1年間に投資できるのは、「つみたて投資枠」で120万円、「成長投資枠」で240万円です。投資で得た利益は恒久的に非課税となるため、効率よく投資で資産を形成できるメリットがあります。
家庭の状況によって、毎月支払える金額は異なります。学資保険やNISAを活用して教育資金を準備する際は、継続することが大切です。そのため、無理のない範囲で積立額を決めるようにしてください。
奨学金や教育ローンの活用
奨学金には「貸与型」と「給付型」があり、上手に活用すれば、家庭で準備する教育費の負担を減らせます。
| 奨学金の種類 | 貸与型 | 給付型 |
|---|---|---|
| 採用基準 | 低い | 厳しい |
| 採用人数 | 多い | 少ない |
| 返済義務 | あり | なし |
| 奨学金の例 | 第一種(利子なし) 第二種(利子あり) | 給付奨学金制度 |
奨学金には、国や自治体が実施する「公的奨学金」や、学校独自や育英団体などが実施する「民間奨学金」があります。そのうち、公的奨学金である「日本学生支援機構」は、大学生の3人に1人が利用しているとも言われています。
奨学金を利用する際は、将来のライフプランを見据えて上手に活用することが望ましいと言えるでしょう。
また、教育ローンには「国の教育ローン(教育一般貸付)」と「民間金融機関の教育ローン」があります。奨学金は月額であったり申込期間が限られていたりなど限定的ですが、教育ローンならいつでも申し込みが可能です。
また、子どもに返済の負担をかけないだけでなく、学力が問われることもありません。奨学金制度で条件のクリアが難しい場合は、教育ローンの利用を検討することも教育資金を準備する方法の1つです。
教育費が足りないとどうなる?よくある失敗例

計画的な教育費ができず、資金が不足してしまったときは、以下のようなケースに陥ります。
- 奨学金に大きく頼ることになる
- 老後の生活資金を取り崩してしまう
- 無理なローンや借入で家計が苦しくなる
返済が必要な奨学金は、子どもの将来に大きな負担をかけてしまいます。また、親もいずれは老後生活を考えなければならない身です。老後資金を取り崩すと、決して長くはない老後までの期間、再び資産を形成しなければなりません。
その結果、無理な教育ローンや借入に頼ってしまい、家計が苦しくなるケースは多くあります。
教育費は計画的に積み立てることが大切です。それでも、家庭状況によっては積立が困難な場合もあります。そのため、ローンや借入、奨学金に頼る前にまずはFP相談で教育費シミュレーションをおすすめします。
なお、教育費の準備に不安がある場合、家計の見直しが必要不可欠です。以下の記事では、家計の見直し方法について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

大学までの教育費に関するよくあるQ&A

ここからは、教育費に関するよくある質問を紹介します。
教育費が高額化するにつれ、多くの人が疑問に抱えるようになってきた問題点ばかりです。ぜひ参考にしてください。
Q1:教育費はいつから貯め始めればいいの?
教育費の準備はできるだけ早く始めるのが理想です。出産直後から児童手当を積み立てれば、中学卒業までに200万円以上の進学資金を用意できます。
もちろん途中からでも遅すぎることはありません。例えば中学から始める場合は、大学入学までの6年間で集中的に積み立てることで、必要額に近づけることが可能です。
Q2:教育費はいくら貯めれば安心ですか?
必要額は進学ルートによって大きく変わります。
しかし、「オール公立:約1,300万円前後」「大学だけ私立:約1,700万円前後」「幼稚園から大学まで私立:約2,900万〜3,100万円」など、すべてを事前に貯める必要はありません。半分程度を積立や学資保険で用意し、不足分は奨学金や支援制度で補うご家庭も多くあります。
Q3:2人以上の子どもがいる場合、教育費はどう準備する?

兄弟や姉妹がいると教育費は単純に2倍、3倍とかかります。
児童手当は人数分受け取れるので、それを積み立てると効率的です。また、多子世帯の場合は「大学無償化制度」が使えるケースもあります。詳しくは「大学無償化制度の概要や手続きは?多子世帯の条件・奨学金との併用までFPが徹底解説」の記事で確認してみてください。
Q4:教育費は学資保険とNISAどちらで準備すべき?
学資保険のメリットは、決まった時期に確実に受け取れることです。ただし、運用する利率は低めです。一方、NISAには、長期運用で資産を増やせる期待が持てますが、元本割れのリスクがあることも忘れてはなりません。
教育資金は、子どもを育てる以上、必ず必要となります。そのため、どちらか一方に偏るのではなく、「確実性のある学資保険+成長性のあるNISA」の組み合わせがおすすめです。
Q5:教育費が足りないときはどうすればいい?
学費や進学資金が不足した場合は、奨学金や教育ローンを活用する方法があります。
奨学金には返済不要の給付型もあり、条件を満たせば利用できます。また、国の高等教育の修学支援制度を使えば、授業料の減免も可能です。教育費をすべて家計だけで賄う必要はなく、公的制度を上手に使って負担を減らすことも考えてみましょう。
教育費はFP相談でキャッシュフロー表を使った「見える化」が効果的

教育費で慌てないためには、「いつ」「どれくらい」など教育費のピークを把握することが大切です。ライフプラン表を設計することで、家計管理をしながら教育費の計画が立てやすくなります。
キャッシュフロー表で未来をシミュレーション
「ライフプラン表」や「キャッシュフロー表」を作成すると、次のようなことが分かります。
- 何年後に教育費のピークが来るか
- その時に貯蓄が足りているか
- 住宅ローンや老後資金とのバランスはどうか
教育費の失敗例に、シミュレーション不足が挙げられます。おぼろげながらのシミュレーションでは、お金の管理は難しいと言えるでしょう。
ライフプラン表やキャッシュフロー表で、お金の流れや推移を「見える化」することで、より具体的な教育費のシミュレーションが可能となります。
FP相談で得られるメリット
FP(ファイナンシャルプランナー)は、お金の専門家です。
お金の流れや公的制度、資産形成を得意とするFPに相談することで、より正確なシミュレーションが可能です。キャッシュフロー表でお金の流れを「目で見て理解できる」ため納得しやすく、ライフプラン全体を考えながら無理のない教育費計画を立てやすくなります。
FP相談を利用するメリットは、以下の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

大学までの教育費は最大3,000万円超!制度を上手に活用しよう

子どもが生まれてから大学を卒業するまでに、3,000万円の教育費が必要であると言われるのは本当です。
しかし、3,000万円もの資産は、わずか10年前後で貯めることは至難の業です。そのため、学資保険やNISAを上手に活用し、家計に大きな影響を与えないよう計画的な教育資金づくりが重要となります。
返済しなくても良い奨学金や、多子世帯向けの無償化など、公的な制度を利用することも視野に入れておくこともおすすめです。
FP相談では、無理のない教育資金の準備方法や、「今からじゃ遅い?」と思われるようなタイミングでも、家計に合わせたアドバイスが可能です。教育費で悩まれた際は、ぜひお近くのファイナンシャルプランナーへ相談してみてください。
ライフイベントやライフステージなど、目指すべきものがあるとき、家計に合わせた計画を見つけることが大切です。W&D-Writer&Design-では、ライフプランニングを得意としており、1人ひとりのキャッシュフロ-表で、将来の予測が立てやすくなります。
オンラインによる相談は、ご自宅から足を運ぶことなくお金の悩みを相談できます。なお、初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
FPに相談するなら
W&D-Writer&Design-
独立系FPは、中立な立場でアドバイスをする専門家です。
お金の問題を切り離して人は生きることができません。
お金に関して少しでも不安があれば、ぜひご相談ください。

お金の相談って誰にしたら良いのかわからない・・・
そんなときは、独立系FPに相談すると中立な立場に立って、悩みを解決することができます。
「でも、お金の悩みってどんな内容?」
「料金を支払ってまで相談する必要がある?」
FPは保険や税金、投資や不動産、家計に関する内容まで、幅広いお金に関する知識を持っています。
そのため、専門的な勉強が必要となる知識と経験をもってアドバイスが可能です。
確かにお金を支払ってまで相談することには、抵抗を感じてしまうことでしょう。
それなら、まずは独立系FPの無料相談を利用して、専門的な知識でアドバイスしてもらえるのかをプロに聞いてみてはいかがでしょうか。
| FP相談 | W&D -Writer&Design- | 一般的な 独立系FP |
|---|---|---|
| 相談料金 | 初回無料 | 有料 |
| ライフプラン表 | 作成可能 | 作成しないFP相談がある |
| キャッシュフロー表 | 作成可能 | 作成しないFP相談がある |
| 家計に関連する相談 | FPごとに専門が異なる | |
| 相談方法 | 訪問 オンライン | 事務所 訪問 オンライン |
無料の初回相談では、どのような悩みがあるのかを教えていただきます。これは、漠然とした悩みの中心は何が原因なのかを分析するためです。
相談内容ごとに、改善が必要な部分などをアドバイスさせていただきます。
その後、改善などに対して詳しく分析していくとき、必要に応じてライフプラン表やキャッシュフロー表を作成し、見える変化をご提案させていただきます。ただし、各資料作成には費用が発生します。
「中立な立場の専門家に相談したい」と思ったら、W&D-Writer&Design-の無料相談をご利用ください。